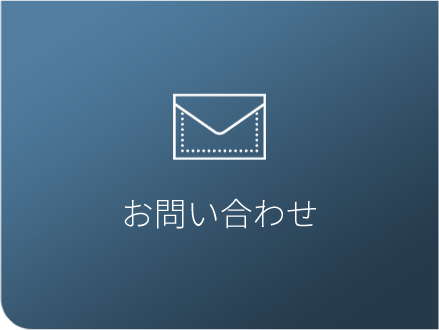人生を変えた「サバニ」は、人々に幸せを運ぶ船。

邊土名 徹平
Teppei Hentona
国頭郡大宜味村 [沖縄県]
邊土名徹平(へんとな・てっぺい)
沖縄県浦添市出身。ヘントナサバニ代表。大宜味村を拠点に、木造帆かけ船「サバニ」を製造しながらクルーズツアーを主宰する。石垣島で観光業に携わるなかサバニと出会い、その美しさと文化的価値に魅せられ伝統技法を継承。2020年に大宜味村に移り独立、沖縄の自然と文化を伝える活動を続けている。
沖縄県大宜味村の塩屋湾から、木造の帆かけ船「サバニ」を漕ぎ出す船大工・邊土名徹平さん。観光業に携わるなかで出会った一艘の船が人生を変え、やがて自身のルーツである大宜味に拠点を構えた。サバニを造り、操り、伝える日々。故郷への深い感謝とともに、その技術を未来へ繋ぎたいという邊土名さんの希望とは。詳しく話を伺った。
一瞬で魅了された、沖縄の海に浮かぶ美しい船「サバニ」
塩屋湾から1艘の帆かけ船がゆっくり沖へと漕ぎ出す。漕ぎ手はビロウ(クバ)の葉を編んだ「くば笠」を被り、帆に当たる風を読みながら手にしたエーク(櫂)で大きく水を掻く。船にはもう一人の漕ぎ手と小さな男の子。その様子は、船が生活の一部だった数十年前の風景を思い起こさせる。
ここは、沖縄本島北部に位置する大宜味村宮城島。自然豊かな「やんばる」と呼ばれる地域だ。船に乗るのは、島に工房を構える邊土名徹平さん一家。
その船「サバニ」は、風とエークによって進む、沖縄伝統の木造帆かけ船だ。邊土名さんは、造り手であり、サバニクルーズツアーにてガイドをする船長でもある。
「サバニに出会ったのは、石垣島で観光業に携わっているときでした。海に浮かぶその姿を見て、なんて美しい船だろうと一瞬で魅了されてしまいました。自然の素材から作られた船が静かに浮かぶ佇まいに、感動したんです」

当時、旅行会社に勤め、石垣島周辺の魅力を国内外に伝えるため、観光素材の発掘を手掛けていた邊土名さん。八重山諸島の島々に足を運ぶなかで訪れたのが、サバニ大工、吉田友厚氏の工房だったという。
「長年探し求めていた、沖縄に貢献できる仕事はこれじゃないかって直感したんです。その瞬間、自分の立場も忘れて『私、この船作ってみたいです』と、後の師匠となる吉田さんにお願いしていました」邊土名さんは笑いながら当時のことを振り返る。
それが、邊土名さんの人生を大きく変える、「サバニ」との出会いだった。
サッカー、音楽、そして観光へ。抱いたのは、故郷に貢献したいという思い
「小さい頃はサッカー一筋でしたね。中学までずっとやってました」
邊土名さんは、グラウンドを駆け回るサッカー少年だった。そして、中学生の頃にはギターを手にし、音楽に夢中になる。高校では仲間とバンドを組み、自作の曲を演奏するように。ライブ活動に明け暮れ、20歳過ぎには、沖縄だけでなく東京のCDショップに音源が並ぶほどのインディーズバンドに成長した。
バンド活動と並行して、CDやビデオのレンタルショップでアルバイトをしていた邊土名さん。そこで気づいたのは「人に喜んでもらえる接客業の楽しさ」だったという。ちょうど、バンド活動に一区切りつけようと感じ始めていた時期でもあった。
「お客様に『ありがとう』と言われるのが嬉しい。ならば、接客の世界に本格的に身を置こうと思ったんです。当時の私にとって、接客業の最高峰として思いついたのが『ホテル』。全国展開する大手ホテルに就職し、その後約10年、全国各地の支店にて経験を積みました」
そのとき、邊土名さんが抱いていたのは、いずれは観光立県である沖縄に貢献したいという思い。自らを育んでくれた故郷に、純粋に恩返しをしたいという気持ちだったという。
そこで、決意したカナダ行き。海外からの観光客も多い沖縄で、コミュニケーションに欠かせない英語力を身につけ、さらに、観光に携わる者として視野を広げたいと思ったのだ。
「カナダは移民国家なので、多様なルーツを持つ人が集まり、さまざまな文化や暮らしがあります。そのなかに飛び込もうと、公園で多国籍の人たちが集まるサッカーに参加したり、アメリカに足を伸ばしてサーフィンをしたり、とにかくいろんな人と交わりながら過ごしました。
そこで感じたのは多様性。一人ひとり違って当たり前、という価値観を得たことは、私の世界を大きく広げてくれました」
ビザの期限である1年を終えた邊土名さんは、観光を通じて故郷に貢献したい、という思いを胸に、迷うことなく沖縄へ帰る。そしてカナダでの経験を活かし、石垣島の旅行会社に就職。仕事をするなかで、サバニとの運命的な出会いを果たした。カナダで培った価値観は、次のステップへと進もうとする邊土名さんを後押ししたようだ。
途絶えかけた伝統を受け継ぐ「サバニ大工」としての日々
旅行会社を退職し、吉田さんに弟子入りした邊土名さんは、サバニ大工としての道を歩み始める。もちろん、沖縄に生まれ育ったが、改めてサバ二と「向き合う」のは初めてだった。
そもそも、サバニの歴史をたどると、約150年前に大木をくり抜く「くり舟」から、複数の板を継ぎ合わせる工法へと変化し、用途は漁業や運搬など多岐に渡った。しかし1950年代以降、エンジンの普及とFRP(強化プラスチック)船の登場により、木造の帆かけサバニは急速に姿を消した。
「注文も少なくなり、サバニ大工も減っていったそうです。そのままだったら、完全に途絶えていた可能性もあったと聞いています」
転機は2000年。座間味島から那覇までの約36キロを渡る「サバニ帆漕レース」が始まったことなどをきっかけに、再び注目が集まった。レースに参加するための新艇注文などが増えたことで、船大工の技術も残った。その流れがあったからこそ、邊土名さんは吉田さんのもとで学ぶことができたのだ。
ただ、その技術習得は容易ではなかった。サバニは金属の釘を使わず、複数の木材を蝶形の木片(チギリ)や竹釘で繋ぐ独特の工法を用いる。1艘を仕上げるのに約250個のチギリや約500本の竹釘をひとつひとつ作り、打ち込む必要がある。高い精度で木を接がなければ、水漏れして使い物にならない。それでも邊土名さんを突き動かしていたのは、自らを育んだ沖縄への思いだったという。


「すべての工程で、先人の知恵を感じることができるんです。技術を習得し、次の世代に伝えていくことができれば、自分なりの沖縄への貢献ができるのではと感じました。
自分の手で木を削り船を造って、大海原に漕ぎ出すということにやりがいやロマンを感じています。だから、コツコツと進めていく作業さえ楽しめているんです」
そして修行を終えた2020年、邊土名さんがサバニ大工としての拠点に選んだのが、大宜味村宮城島だった。
サバニを通して知った、自らのルーツ
邊土名さんが石垣島で修行を積んでいたときに知ったことがあるという。それは、自らの先祖が200年以上前から宮城島で暮らしていたという事実だ。
その後の1955年、戦後の人口増加に伴う開拓事業で、祖父である邊土名朝興氏がリーダーとなり約350人とともに石垣島へ移住。父も宮城島生まれで幼少期から中学までを石垣で過ごしたものの、その後沖縄本島南部に移り住んだため、邊土名さん自身は宮城島や石垣島との縁をほとんど知らなかったのだ。
ところが、大人になって石垣島の旅行会社に勤めていた際、偶然にも祖父たちが築いた村にたどり着く。現地で「あんたは邊土名朝興さんの孫ね?当時、朝興さんが粘り強く交渉してくれたおかげで、今のこの村があるんだよ」と声をかけられ、祖父の功績を目の当たりにしたことで、自らのルーツを強く意識するようになった。
「ご先祖様に導かれているとしか思えませんでした。石碑に祖父の名が刻まれ、公民館に写真が飾られているのを見て、さらには初めて会う方にあたたかく接してもらえて。感謝せざるを得なかったですね」
さらに修行中、大宜味村出身で、同じく開拓移民で石垣島に移り住んだ近所の人から「あんたの故郷は大宜味だよ。塩屋湾でサバニをやったら上等よ」とも告げられた。
歴史を辿るように訪れた塩屋湾は、豊かな自然に囲まれ、古くからの記憶を残す土地だった。「ここで伝統を繋ぐことが、自分にとっての使命かもしれない」。そう感じた邊土名さんは、大宜味村宮城島での独立を決意する。
地域の人々も温かく迎え入れた。砂浜で船の手入れをしていれば、かつての漁を思い出しながら「懐かしいさ」と声をかけてくれる。帆を上げて走れば「昔の風景そのものだ」と喜ぶ声が聞こえてくる。近い親戚は残っていないものの、「邊土名一族」として親しみを持って受け入れ、応援してくれる人も多い。
「思いがけずいろんな方に出会って、自分の祖父や父が辿った道を遡るようにここに導かれ、サバニを造って暮らしている。本当に幸せなことだと感じています」
サバニで感じる海の豊かさと先人の営み
大宜味村のなかでも、塩屋湾周辺の集落にとって、年に一度の大きな行事がある。それが国指定重要無形民俗文化財である「ウンガミ(海神祭)」だ。豊漁や五穀豊穣を祈願して行われるこの祭では、色鮮やかに塗られたハーリーを男性たちが漕ぎ、集落ごとに速さを競う。岸に向かって進むハーリーを太鼓や歌で迎えるのは女性たちだ。
そんな故郷の伝統についての話を、邊土名さんはサバニクルーズツアーの参加者たちにわかりやすく伝える。もちろん、サバニの歴史や、受け継がれた技術も。
「現在、さまざまなマリンアクティビティが多くの方に親しまれていますが、ここ沖縄で生まれ育まれてきた船で沖縄の海を感じることは、サバニならではの魅力だと思います。船に乗りながら、地域の歴史や、先人の営みにも思いを馳せることができます。
もちろん、風の力で走る疾走感もサバニの魅力の一つです。木のぬくもりや風の心地良さを感じながら海の上を滑らかに進んで行くときは、地球と一体になっているような感覚になりますね」

風が止んだときには、誰もが漕ぎ手になる。大人も子どももエークを持ち、声を合わせて漕ぎ進めていく。最初は遠慮がちだった子どもも、いつの間にか漕ぎ手の一人として声を出し、笑顔でエークを操っている。普段は人見知りだという子どもが、驚くほど自然に自分を解放し楽しんでいる。そこに生まれるのは一体感だ。沖縄の美しい海と、木のぬくもりを感じるサバニが、その繋がりを育んでいるのだろう。雄大な自然に包まれたとき、人は本来の自分に還るのかもしれない。
未来へ繋いでいきたいものは何か?
最後に、邊土名さんに未来に繋いでいきたいものは何か、と尋ねた。
「サバニの文化を次の世代に繋いでいくことですね。まずは魅力を発信しながら、こんなすばらしい船があるということを知ってもらいたい。私自身は、サバニ大工としての技術をもっと磨いていきたいと思っています。
まだまだ駆け出しの身ですが、将来的には技術を継承していくことで故郷に貢献できれば、こんなに嬉しいことはありません。一人の職人として憧れられる存在になれるよう努力していきたいです。この伝統の繋ぎ手が少しずつでも増えることを願っています」
サバニと出会い、自らのルーツを知り、それをきっかけに家族をつくった邊土名さん。そして今、妻や息子とともに海に漕ぎ出し、大自然を満喫している。
「私の人生を大きく変えたサバニは、幸せを運ぶ船だと信じているんです。1人でも多くの方にサバニに触れてもらい、それぞれの人生に良い風を吹かせることができれば、と思ってます」
邊土名さんの言葉からは、沖縄への深い愛情と誇りを感じる。そして、伝統を繋いでいくという強い意志も。ただその表情から感じるのは、固い使命感ではなく、志とともに歩みたいという願いだ。そして、おおらかに伸びやかに、故郷で生きていきたいという希望だ。