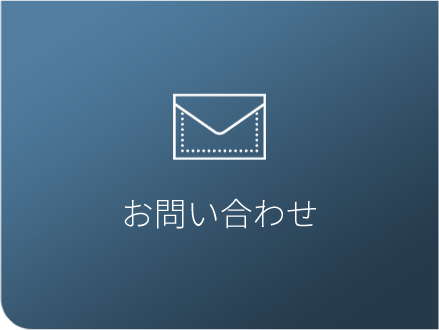経営危機から再生、そしてオーベルジュへ。宮浜温泉「庭園の宿 石亭」が思い描く未来

上野 純一
Junichi Ueno
廿日市市 [広島県]
上野 純一(うえの・じゅんいち)
広島県廿日市市出身。宮浜温泉「庭園の宿 石亭」2代目当主。「あなごめし うえの」4代目。大学卒業後に家業に入り、廃業寸前に追い込まれていた宿の再生を果たす。「庭を守れ、宿を大きくするな、兄弟仲良く」という父の教えに従い、庭・料理・部屋など、ここでしか味わえない独自性を体現。「日本のオーベルジュ」を目指し、宮島口の活性化にも尽力する。
瀬戸内の海を望む宮浜温泉「庭園の宿 石亭」。国内外から高い評価を受ける庭は、訪れる人に深い安らぎを与えてきた。その石亭を率いる2代目、上野純一さんは、父の遺志を受け継ぎながらも時代に即した改革を重ね、「ここにしかない時間」を育んできた人物だ。常に先を見据え歩んできた上野さんが未来に思い描くものとは。
まちの将来を見据え誕生した宮浜温泉。そして、「石亭」創業へ
国内屈指の庭を有する「庭園の宿 石亭」。国内外から訪れる多くの宿泊客は、四季折々の移ろいを感じる庭を心ゆくまで楽しみ、また、12の趣ある客室や食通をも魅了する料理を通じ、「ここでしか味わえない時間」を堪能する。上野純一さんは、その2代目当主だ。

「宿のことをお話するには、まず昭和39年の宮浜温泉成り立ちまで遡って、ご説明しなければなりませんね。
日本中が戦後の復興を目指し活気に満ちていた当時、私の父は、宮島対岸に位置する大野町(現在の廿日市市大野)の町長でした。まちの将来を考え、宮島観光で訪れたお客様にこのまちにも足を運んでもらおうと、観光拠点立ち上げに心血を注いだ人です」
その思いは、5ヵ年計画「新宮島構想」として一大プロジェクトとなり、大掛かりな造成工事によって、まちは次第に変化していく。その際、掘り出されたのが、宮浜温泉である。
ただこの一帯は、新宮島構想で人の手が入るまで、戦後約20年にわたり荒れ果てた状態だったという。
「昭和20年9月、原爆投下からわずか1ヶ月後に広島を大きな台風が襲いました。世にいう『枕崎台風』です。まちの高台にあった陸軍病院も流され、原爆の被害調査で宿泊していた、京都大学の優秀な若手研究者たちが犠牲になったんです。今の宮浜温泉に、再び息を吹き込もうと尽力したのが父でした。

実は石亭の庭は、台風での地形変化をそのまま利用しています。また、庭の池の真ん中にある大きな岩は、明治の初めに山崩れで落ちてきたものだと言われています。ですから父は、この地域の歴史とともに、宮浜温泉や石亭を整備していったわけです。『この庭は、水災害の復興の証だ』と、よく語っていたものです」
石亭が創業したのは、宮浜温泉の開湯直後。地域の未来と庭を守ることを使命に、宿としての歴史をスタートする。
希望と覚悟で向き合った、石亭再生への道
創業当初の石亭は、宿泊客に湧いた。高度経済成長期の真っ只中、庶民の暮らしに「旅行」という余裕が出てきた頃である。しかし、10年も経たないうちに、オイルショックが訪れる。開湯時には十数軒あった宿も、気付けば4軒に。大衆宿のイメージが強かった石亭は、なんとか暖簾を掲げている、という状況が長く続く。
一方、上野さんは大学進学で東京へ。家業の様子を感じ取ってはいたものの、「逃げ出す」ために故郷を離れたいという気持ちもあった。だが「継がないのであれば宿をたたむ」との父の言葉で、跡取りになることを決意。大学4年生のときには、東京で石亭の案内を担ってくれる旅行代理店を探そうと奔走した。思ったような結果は得られなかったものの、旅行業界における営業方法は、身に付けた自信があった。
そして帰郷。覚悟はしていたものの、宿の経営状態は目を背けたくなるものだった。さらに、宮島口に店を構えていた「あなごめし うえの」も状況は同じだった。
「すでに結婚していた私にとっては、本当につらいばかりの現実でした。ただ、そうも言っておられません。契約が取れるまでは帰らない、という覚悟を決めて、名刺と宿の写真を持って大阪に向かったんです。そして、3日目に伺ったある旅行手配案内所が、石亭の案内所になってもいいと。それはもう嬉しかったですね。
とはいえ、しばらくは営業の日々。行った先々でいただくアドバイスは積極的に取り入れました。料理の質を上げなければ、と思ったのもそのときです。とにかく必死でしたね。
すると、大阪からも地元からもお客様が増え始めたんです。知人や友人、父の代からお世話になっている方が情けをかけてくださったということもあります。少しずつですが、評判も上がっていきました」
その後、上野さんの弟が経営に加わり、石亭の「変革」はさらに加速する。良いと感じたもの、心に響いたものはすぐに取り入れた。テーブルクロス1枚、塗り盆1つに至るまで、丁寧に心を配って吟味。すると、面白いようにさらに客足が伸びていった。さらに、全国トップレベルの宿経営者の仲間たちからの学びが、上野さんを当主として成長させていく。
「当時の目標は、弟と二人で『広島で一番有名な旅館にする』こと。今思うと、非常に若者的な発想ですよね。
ですが、実際に宿を引き継いだときが最も大変でした。料理長はじめ従業員の入れ替えを行ったんです。石亭をより良くするためには、2代目である私が、ともに宿を盛り立てていきたいと思える人材を選ばなくてはならない。とてもつらい判断でしたが、腹を括りました」
そのとき、上野さんの指針となったのが、父からの言葉だったという。「庭を守れ、宿を大きくするな、兄弟仲良く」。おかげで、現状にどう磨きをかけ、どこを掘り起こすべきか、というコンセプトが整ったという。

「以来、半年に一度は1週間の休みをいただいて、厨房設備やお風呂の手入れ、それから2部屋ずつの改修を繰り返しています。ああでもない、こうでもないと悩みながら整えていくわけですが、それがコピーライターの目に止まり、『すべての部屋が違っておもしろい』と評価していただきました。
さらに、庭から見える各部屋の様子。本来ならプライバシーを守るために隠すのが宿としては常識です。ところが、ある方から『部屋も景色になっている』と指摘されたことで、オンリーワンの個性だと気付きました」
それらを積み重ね、石亭は大きく生まれ変わった。しかし、「石亭のスタイルが形作られるのは、これからが本番です」と、上野さんは意気込む。
日本のオーベルジュへ。石亭の新たな挑戦
「すでに20年前に、石亭を『日本のオーベルジュ』にする、という計画を立てていたんです」
オーベルジュとは、本格的な食事が楽しめる宿泊施設を備えたレストランのことで、中世フランスが発祥とされている。メインは宿泊ではなく「食」。
そこで石亭は、才能ある若手料理人を招き入れ、彼の可能性を信じ、思う存分料理に打ち込めるよう環境を整えている。そのおかげで、食の評判は上がり続けているという。

「うちの宿は、各部屋でゆっくりと食事を楽しんでいただきますので、部屋まで料理を運び、お客様が口に入れる瞬間が最高の状態でないといけません。料理長は、そこまで計算して調理を段取ります。前菜、揚げ物、焼き物など、すべてにわたって細かい気遣いができる彼は、オーベルジュを目指す石亭にとってなくてはならない存在です。
月に一度来られるお客様からは、毎回少しずつ料理が進化している、ますますおいしくなっているとお褒めいただきます。これは、有名レストランや料亭でもあり得ないことです。
近年では、有能なソムリエも迎え、ワインやノンアルコールドリンクと食のペアリングも、新たな楽しみ方として提案しています。
部屋を目的に宿泊していただくのもありがたいですが、私としては、食事を楽しむためにお越しいただきたい。部屋は『寝るだけ』の場所でもいいと思っているんです。これが石亭の新たなステージですね」
「日本のオーベルジュ」に向け、石亭は確実に布石を敷いている。
「する庭」を体験してこそわかる、最高の過ごし方
石亭の庭は、アメリカの庭園ジャーナル誌(Journal of Japanese Gardening)の日本庭園部門で、4位を誇る。しかも10年以上にわたって。京都の名刹の枯山水や有名美術館の庭園など、数ある「庭」のなかで4番目に評価されることは快挙だといえる。理由は、「見る庭ではなく、する庭だから」と、上野さんは説明する。


「この庭は、実際に立ってみて初めて良さがわかります。目を向ければ、宮浜の海と沖にある宮島、振り返ると経小屋山が望めます。さらに、各部屋の佇まいが樹木や植物と一体となっていることに気付くはずです。部屋の窓から見えるお客様の姿も、植物や手すりなどが緩衝帯になり、丁度良い具合に隠れています。それを、『いい距離感だね』と評価していただいたこともあります。庭から眺める近過ぎず遠過ぎずの距離感が、目にするものすべてを景色に変えてくれているんだと思います」

庭から直接アプローチできる「石亭回遊」も、宿泊客の遊び心を刺激する。4か所のパブリックスペースには多種多様な本やレコードが並ぶ。北欧の美しい椅子に腰掛け、酒やコーヒーを手にくつろぐ時間は、石亭ならではのもてなしだ。
「そこから眺める風景も、時間とともに変化します。また、歩くことで景色の変化も楽しめます。自ら関わることで多くを感じ取れる。それが石亭の『する庭』です」
ここ数年の上野さんのキャッチコピーは「2泊するための宿」だという。2泊することで、庭も、食事も、部屋もじっくりと堪能することができるからだ。もちろん、食事のメニューはどれ一つとして同じものはない。そこから得られる充実感、満足感は言うまでもないだろう。
「石亭は日本のオーベルジュ」、そう捉えている宿泊客はすでに多くいるはずだ。
未来へ繋いでいきたいものは何か?
最後に、上野さんに未来へ繋いでいきたいものは何か、と尋ねた。

「現在、宮島口は、宮島にいくための通過点に過ぎません。その問題解決が、私のもう一つのライフワークですね。
解決には、やはり『食』が欠かせないでしょう。例えば、宮島の観光客も、夕方になると島内の食事処が限られてしまうので、宮島口に戻ってきます。ただその受け皿がない。『あなごめし うえの』も、残念ながら夕方には閉めてしまいます。もし、立ち寄れる場所を増やせば、宮島口の回遊性も上がり、魅力的な街路になるはず。石亭やあなごめしうえので培った『食』のノウハウを活かすことも考えているところです。
ただ、あなごめしうえのは、そのなかでひっそりと息付いていくだけでいい。変わらぬ旨い穴子を味わっていただく。その役目は、次の世代にバトンタッチしていくつもりです」
100年以上にわたり、宮島口という場所で商いを行ってきた上野さんだからこそ、思い入れも強い。次の世代への期待を込めながらも、大きな責任感が伝わってくる。
上野さんは最後に歴史的な事実も教えてくれた。宮島は「神の島」であり、墓を作ることは認められていない。そのため、島内で亡くなった人は、宮島口周辺で埋葬されることが常だったようだ。
このことを伺い、宮島口は宮島への単なる玄関口でも、ましてや通過点でもないと感じる。間違いなく、宮島の一部なのだ。だからこそ、「素通り」ではなく、歴史ある場所として立ち止まるべきなのだろう。
次の100年へと歩みを進める石亭、そして宮島口の変化にも、期待が高まる。