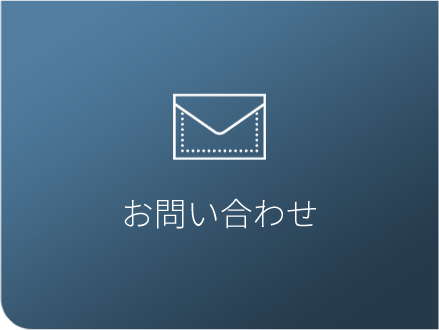つくる人、支える人、伝える人がともに拓く、会津本郷焼の次の100年

松田 純一
Junichi Matsuda
会津 [福島県]
松田 純一(まつだ・じゅんいち)
東京都出身。会津本郷焼事業協同組合事務局。合同会社JERK代表。5歳の時に会津地方に移り住む。東日本大震災をきっかけに、故郷の復興に貢献したいとの思いを持ち、縁あって会津本郷焼事業協同組合事務局の一員となる。現在、会津本郷焼のPRに取り組みながら、会津美里町の地域振興にも力を注ぐ。
会津美里町で400年以上の伝統を受け継ぐ会津本郷焼。窯元ごとに異なる多様な個性と職人の技術は、閉鎖的でありながらも懐が深いと言われる会津人気質によって静かに育まれてきた。その魅力を広く伝えようと活動しているのが、異業種から転身した松田純一さんだ。素人だからこそ感じる、焼き物の価値と地域の課題。人と人との繋がりを大切にしながら、まち全体で会津本郷焼の未来を拓いていきたいと話す松田さんに、その思いを伺った。
震災を機に、導びかれるように会津本郷焼と関わる道へ
福島県会津地方の会津美里町。県内陸の会津盆地に位置するこのまちは、北部に肥沃な平野が広がり、その奥に目をやると、会津地方を代表する名峰、磐梯山を望める。盆地特有の夏の暑さ、冬の豪雪と厳しい環境にありながらも、四季折々の自然美は訪れる人の心を穏やかにしてくれる。
会津美里町を構成するのは、寺社仏閣が並ぶ会津高田、ブドウ栽培が盛んな新鶴、そして、東北地方最古の窯場とされる「会津本郷焼」が伝統を紡ぐ会津本郷である。
ここで、会津本郷焼事業協同組合(※以下「組合」)の事務局として業務に携わっているのが松田純一さんだ。5歳のとき、父親がペンションを開業したことをきっかけに、東京から磐梯山の麓にある裏磐梯へと移り住んだ。
会津本郷と裏磐梯は、車でわずか1時間ほどの距離。しかし、焼き物にそれほど興味がなかった松田さんは、当初、このまちを訪れるのは初めてだと思っていたそうだ。
「会津本郷焼に関わって間もない頃、まちの風景を目にするたびに、自分の記憶と重なるところがあったんです。両親に聞いてみると、東京から移ってきたばかりの頃、会津本郷で開催されたウォークラリーに家族で参加したことがあったと。しかもその頃、私が使っていたお茶碗は、会津本郷焼の窯元『流紋焼』さんのものだったそうなんです。
実は、幼い頃からこのまちとの繋がりがあったと知って驚きましたね」
そんな松田さんが会津本郷焼に関わるようになったのは、どういう理由からだったのだろうか。

「震災をきっかけに故郷の復興に携わりたいと思い、会津美里町の復興PRキャラバン隊の一員になったんです。会津本郷焼を意識するようになったのは、まちの特産品をPRする活動を通して。その後、キャラバン隊の任期が終了するタイミングで、組合で働いてみないかと声を掛けていただきました。
焼き物についてはまったくの素人でしたが、国の指定を受けている伝統工芸品に関わる仕事に就く機会は、そうそうないと思ったんです。人と違う仕事ができることにも興味が湧きましたし、純粋におもしろそうだなと感じましたね。
ただ、正直なところ、いまだに焼き物についてはそれほど詳しくないんですよ」と、やわらかな笑顔で話す。
なにかに導かれるように会津本郷焼と関わることになった松田さんだが、「何が自分の役割だろうか」と模索する時期もあったと言う。そんなとき、ここが居場所だと感じられたのは、周囲の支えがあったからだ。
「組合の方はもちろん、地域のみなさんもとても温かく接してくれました。見守りながらも育ててくれているという感覚がありましたね。恩返ししたいという気持ちは、今も変わりません」
組合の事務局として会津本郷焼に関わりながら、2020年に自身の会社、合同会社JERKを立ち上げたのも、そんな気持ちがあったからだ。地域全体を盛り上げたいと、会津本郷焼を中心に据え、組合の活動を外枠から支える取り組みにも力を注いでいる。
訪れる理由を、“焼き物だけ”から“まち全体”へ
会津本郷焼の発祥は、400年以上前の安土桃山時代。戦国の世の終盤、徳川家によって江戸幕府が開かれる直前の頃まで遡る。会津若松城(鶴ヶ城)の藩主が、雪国の厳しい寒さにも耐え得る屋根瓦を作る目的で、播磨国(現在の兵庫県)から陶工を招き、技術を根付かせたことに始まる。その後「会津本郷焼」という名で会津藩の御用窯になり、時代とともに形を変え庶民の暮らしの道具としても浸透していった。なかでも、郷土料理、にしんの山椒漬けに使う「にしん鉢」は有名だ。
最盛期には100を超える窯元があったと言われるが、実のところ、全国的に見るとその存在はあまり知られていない。理由には、閉鎖的とも言われる会津人の気質があり、東北地方を中心に広まるに留まった。そして、他の伝統工芸と同じく後継者不足に見舞われ、現在は12の窯元を残すのみとなっている。
そこに身を置き、広くPRしていくことを任された松田さん。着目したのは、半径1kmのコンパクトな範囲にそれぞれ作風の異なる窯元が集まっているという、会津本郷焼ならではの特徴だった。
「すべての窯元が、昭和の雰囲気を残す『瀬戸町通り』から枝分かれした細い路地に点在しています。陶器もあれば磁器もあり、また、土そのものの色合いを活かす作風や、釉薬や色彩で独自の世界観を表現する作風など、スタイルは実にさまざま。窯元ごとに受け継がれた、唯一無二の個性に触れることができる、それが会津本郷焼の特徴です。

かつては、他の産地と違い、素材や技法、焼き方に「定義」がないことが課題とされたこともあったようですが、今ではそれを多様なあり方を受け入れる『会津本郷焼らしさ』としてアピールしています」
この地に窯を構え、作陶したものであれば会津本郷焼を名乗れる、という自由度にも、閉鎖的である一方、懐が深いと言われる会津人気質が影響しているのかもしれない。
ただ、関われば関わるほど課題も感じるようになった、と松田さんは続ける。
「県外の焼き物の産地を視察したことがあったんです。すると、窯元だけでなく、カフェやレストラン、休憩所など、私のようにそれほど焼き物に詳しくない人でも、一日を通して楽しめるような場所がありました。
片や会津本郷焼は、限られた地域にすべての窯元が集まっていて、見学するには便利ですが、それ以外に立ち寄れるところがない。地域全体に視野を広げ、 産地を丸ごと満喫できるような魅力作りが必要だと感じました」
その取り組みの一つが、松田さんが自身の会社で運営する「COBACO」だ。町内の空き店舗をリノベーションして開設したこの施設では、まちの休憩スポットとしてカフェを営んでいる。また、雑貨販売やレンタルスペースもあり、立ち寄った観光客の思い出作りを後押ししている。

伝えたいのは、受け継がれた生きた技と職人の魅力
「さらに、日々作陶に打ち込む職人たちの魅力を知っていただこうと、新たな取り組みも広がっています」
それが、丁寧に時間を掛けた窯元巡りだ。観光客は作陶の様子を間近で見ることができ、普段はなかなか接点のない職人との会話も楽しめる貴重な機会となっている。

「私が素人だからこそ感じることなのですが、職人が当たり前に行っている作業は、一般の方からすれば非常に特殊。まったく想像もつかない世界です。
例えば、急須を作る工程ひとつをとっても、ろくろを回す作業や、各パーツを繋いでいく作業もあって、いたるところで技術力の高さを目の当たりにします。
だからこそ、職人の普段の様子を見学していただきたいんです。わかりやすく言えば、旭山動物園の行動展示のようなイメージでしょうか……。生き物本来の姿を観察するように、ありのままの姿を丁寧に見ていただく。真剣な眼差しや手の動き、息遣いといった『生きた技』に触れてもらうことで、焼き物は単なる器ではなく、職人の思いが込められた特別な存在として心に残るはずです」

また、窯元巡りの際には、職人と参加者との繋がり作りにも気を配っていると言う。ただ、その際にはちょっとした工夫も必要などだとか。
「会津の人はもともと口下手な方が多いんです。職人となるとなおさらで、なかにはまったく喋らない方もいて、正直戸惑うこともあります。
そこで、参加者を案内する際には、作陶の工程や作業について、私からできるだけ具体的な質問を投げかけるようにしているんです。すると、だんだん職人の気持ちもほぐれてきて、次第にわかりやすく説明してくれるようになります。そのうち参加者も加わって、会話が弾んでいくんです」
めざしているのは、職人の人となりを知って、彼らの魅力を感じてもらうこと。松田さんは、それをきっかけに職人のファンが増えればと期待している。
さらにその思いから、職人と観光客の「繋がり」をさらに意識した企画も構想中だ、と続ける。
「考えているのは、1年掛かりの陶芸体験なんです。
参加者は定期的に窯元に通い、職人の指導を受けながら、自ら土を練って形にし、乾燥、仕上げ、施釉などすべての工程を行う。その後、作品を窯に詰め、夜通し行われる窯焚きを職人と一緒に見守りながらお酒を酌み交わす……、という内容です。
参加者にとって、時間を掛けて仕上げた作品への思いはひとしおのはず。なにより、職人との間に育まれた絆は、生涯の宝になるに違いありません」
未来へ繋いでいきたいものは何か?
最後に、未来に繋ぎたいものは?と、松田さんに尋ねてみた。
“職人やこのまちに暮らす人たちとともに、地域全体で、会津本郷焼を次の100年へと繋いでいきたい”
「まずは気軽に、会津本郷を訪れてほしいですね。古い街並みを歩くだけで、400年以上受け継がれてきた伝統を感じることができます。
そして、職人や地元の人たちと触れ合い、ここの暮らしや人のあたたかさも感じてもらえたら嬉しいです。そうすれば、一度きりではなくまた訪れたいと思えるほど、このまちへの深い愛着を持ってもらえるかもしれません。
会津本郷焼はもちろん、それを支える人もまちもすべてを好きになってほしいと願っています」

聞けば、「必ずお気に入りの窯元がある」と言われるほど、この地域の人たちから愛されている会津本郷焼。長い年月をかけて地域で育まれ、大切に守られてきた伝統だからこそ、訪れる人の心にも強く響くはずだ。
松田さんはさらに、会津本郷焼が生き続けるためには、後継者の育成が欠かせないと意気込む。そのためには、地域の人たちはもちろん、職人を支えるファンの存在も重要だ。会津本郷焼を愛するすべての「人」が関わり合い、繋がってこそ、新たな担い手を育てる土壌が生まれる。そして、会津本郷焼を未来へと導いていくことができるのだろう。
「この仕事は好きでやっているだけ。自己満足ですよ」
松田さんは控えめに笑う。だがその情熱は間違いなく、この焼き物の里に新たな風を吹き込んでいる。彼もまた、会津本郷焼を未来へと導く大切な一人なのだ。