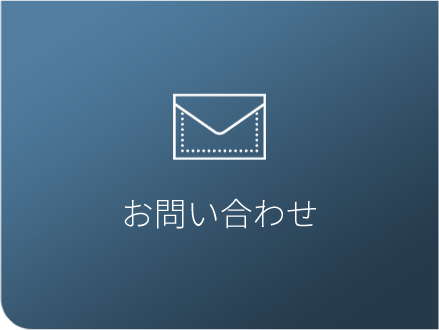400年以上にわたり紡がれてきた紙布の伝統文化を、さらに後世に繋いでいく

津島 久人
Hisato Tsushima
江田島市 [広島県]
津島 久人(つしま・ひさと)
広島県江田島市、能美島出身。津島織物製造株式会社、代表取締役であり5代目。幼い頃より紙布織物という伝統文化を間近に見て育つ。専門学校卒業後は家業ではなく壁紙職人の道に進むが、仕事を通して紙布の価値を再認識し、故郷へ戻り父である4代目に師事する。現在は紙布づくりを行いながら、工場見学ツアーなどを開催し、伝統文化の素晴らしさを広く伝える取り組みも行う。
400年以上の歴史を持つ「紙布」。多湿な日本の気候にも適した紙布をつくり続けているのが、江田島市能美島にある津島織物製造株式会社の5代目、津島久人さんだ。伝統文化を生業とする家に生まれたが、一旦は違う道を選択し島を離れる。その後、紙布の価値に気付き家業を継承、今に至る。時代の流れとともに紙布産業が衰退する中、後世にもその文化を残していこうと紙布づくりを続ける津島さんの作品への評価は高い。ここ能美島で100年後、200年後にも紙布を繋いでいきたいと願う津島さんの熱意の源に迫ってみた。
瀬戸内海の島で積み重ねられた、紙布づくりの技
「紙布」をご存じだろうか。読んで字の如く、「紙」を織ってつくられた「布」のことで、400年以上の歴史を持つといわれている。広島湾に位置する広島県江田島市の能美島には、日本でも二社しか現存していない紙布工場の一つが今でも製造を続けている。

「多いときには全国に100以上の工場があり、職人も育っていたようですが、紙布の需要が減るに従って、工場も閉鎖されていきました」
そう語るのは、津島織物製造株式会社の津島久人さん。1890年の創業以来、織物一筋に歴史を繋いできた会社の5代目だ。
津島織物は綿織物製造を生業として会社を起こし、紙布をつくり始めたのは昭和に入ってからだ。軽くしなやかな肌触りが夏の着物地として重宝されていた紙布が、パナマ帽の生地としてアメリカに多く輸出されるようになり、2代目である津島さんの曽祖父が製造に踏み切ったという。そして昭和30年代半ば頃、ある商社が壁紙にも使用できると目を付けたことから、欧米のインテリアに多用されるようになった。

津島織物が紙布の材料として使用しているのは針葉樹から精製された紙だ。もともとは柔らかく張力もないが、それを短冊状にして撚ることで織物にも耐え得る糸になるという。しかも調湿効果を持つため、雨の日、晴れの日と呼吸を繰り返し、湿気が多い日本の気候にも即している。
「古い文献が残っているんですが、糸を顔料で染める技術を考案したのは曽祖父なんです。もともと特徴的な風合いを持つ丈夫な紙布ですが、糸を染めたことで、さらに表情豊かになり、なおかつ強度も増しました」
縦糸と横糸に顔料で染めた糸を使い、格子柄や縞柄など様々な模様に織り上げられた津島織物の紙布は、最盛期には年間50万m以上も生産され、壁紙として多くの人を魅了した。現在もなお、製造する紙布の9割は壁紙として使用されているが、ビニール素材の手軽な製品が登場して以来、その生産量は次第に少なくなっている。
島を離れ、再び島へ。
改めて感じた、5代目としての宿命
瀬戸内の温暖な気候と、悠然と広がる海からの恩恵が豊かな能美島で育った津島さん。幼い頃より、一定のリズムで聞こえてくる織機の音を耳にしながら、紙布ができあがる様子を間近で見てきたが、初めて選んだ仕事は壁紙職人だったという。

「父親から『継いでほしい』と言われたことは一度もなかったんです。ただ一つ、『手に職を』とだけは言われてましたので、学校卒業後は実家を離れ、壁紙の仕事を15年程続けました。その中で、大量生産されるビニール素材の壁紙が主流になっていく様子を目の当たりにして、紙布の価値を改めて感じるようになりました」
一度は違う道を選択し、島を後にした津島さんだったが、家業を継ぐことを決意し帰郷。その後数年間、父親と仕事を共にすることになる。
「紙布織物の技術力の高さを見るにつれ、やはり受け継いでいくべきものだと感じました。もちろん需要が減ってはいますが、この唯一無二の伝統を繋いでいくのは、5代目である私の宿命かもしれないと思ったんです。
ただ、父親から教えてもらうことはほとんどなかったですね。昔気質の職人でしたから、知識も技も『見て覚えろ』という感じ。私も壁紙職人として、先輩方の仕事ぶりを見ながら少しずつ技術を身につけていきましたので、こちらからも色々と質問することはありませんでした」

さらに、代々、「考えるのではなく感じる」というものづくりとの向き合い方を貫く津島織物。明治、大正、昭和と受け継がれてきた技術を、5代目として生まれ持ったDNAで感じ取っていった島津さんは、工場内の空気や温度、織機の微妙な動きや音の変化にも自らの感覚で対応している。
頭に浮かんでいる紙布の模様を表現しようと、顔料で染めた糸を組み合わせて織った紙布よりも、たまたま手元にあった残糸をそのときのインスピレーションで織ったものの方が、表情豊かに仕上がることが多いというのも、創業以来紡がれた芸術的なセンスが、無意識のうちに紙布に表現されるのかもしれない。
「工場横の倉庫には、70年以上前に織った紙布が今でも保管されているんです。柄が素晴らしく、顔料の色も褪せずに残っています。おそらく、50人程の職人を抱えていた時期につくったもので、その技術力の高さには目を見張ります。今でも、その柄を再現するほどすばらしい作品です」
生まれたこの島で紙布をつくり続け、
その素晴らしさを伝えていく

2020年より、正式に津島織物を継承した津島さんは現在、SNSでの発信にも力を入れている。伝統文化を絶やさないためにも、若い世代に知ってもらうことが大切だと考えているからだ。また工場見学と手作り体験も随時開催。1時間ほどかけて、紙布の歴史から、紙布が織り上がる過程までを機械を動かしながら丁寧に解説する。その甲斐あって、全国各地からデザイン関係者やエンドユーザーが見学に訪れるようになってきた。
「何百もの縦糸が組まれ、そこに横糸が織り込まれていく様子を、皆さん食い入るようにご覧になります。できあがった紙布も実際に手に取り、その風合いの良さに感動されます。中には帰りの船を1便遅らせてでも、時間を掛けてじっくり見学したいと言われる方もいらっしゃるほどです。大量生産ではできない繊細な作業を目にすることで、この島で育まれてきた文化の価値に気付かれるんだと思います」

見学者には、紙布が地球環境にやさしいことも必ず伝えている。土に還り、いずれは大地の肥料にもなる紙布は、その原料が自然由来の紙だからこそだ。自然の恵みから紡がれた糸で織られた布が、いつの日かまた自然に戻っていく。
その有機的な流れも評価され、上質な風合いを持つモダンな柄の紙布は、近頃では高級ホテルや高級ブティックの壁紙に指名されることもある。さらには、織り目の美しさとデザイン性の高さからハイレベルなハンドバッグにも使用されたりと、徐々に注目度も増している。
紙布を使った商品開発にも積極的に取り組んでいる。広島県内の企業と手がけた紙布バッグは、2022年度には「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」で地方創生賞を受賞。また「まずは気軽に購入できる紙布雑貨を通して、紙布の魅力を知ってほしい」と紙布タオルや紙コースターの試作を重ね、工場見学の際に購入できるようにしている。
「規模が小さくなっても、本物の良さを理解してくださる方からの注文が途絶えることはありません。このことは、紙布をつくり続ける意欲にも繋がっていますし、なにより、良いものをつくり続けられるこの環境は、津島織物の財産だと感じてます」

曽祖父が紙布をつくり始めた頃は、数ある紙布工場の一つにしか過ぎなかったが、培われてきた技術力と芸術性の高さから、現在では「津島織物の紙布」として選ばれるように。
130年余りの歴史の積み重ねは、ここ能美島だからこそ可能だったとも津島さんは話す。
「この島には美しい海があり、緑豊かな山もあります。自然に囲まれた環境が、紙布づくりにも影響していると思うんです。都会のように人や物が多くないからこそ、自分と向き合い、自ら考え、決断する場面も多い。感覚を研ぎ澄ますことができるこの島は、ものづくりに最も適している環境だと思います。私はこれからも、生まれたこの島で紙布づくりを続けていきたい」
未来へ繋いでいきたいものは何か?

最後に、津島さんが未来に繋ぎたいものを聞いてみた。
“毎日一人ずつでも、この紙布を知ってもらいたい。そのためには種をまき続ける。いつか、その種が花を咲かせる日が来ると信じたい”
「一度島を出て、違う仕事をしたおかげで、私自身が紙布の価値を改めて認識しました。この貴重な伝統文化を100年後、200年後にも繋いでいきたい。今は強くそう思っています。ただ一つ、紙布の需要が減ってきたのと同時に糸のつくり手も減っていて、今後いつまで、製造が続けられるかわかりません。
心配ごともありますが、私にできることは、妥協せず紙布職人としての信念を貫くこと。そして、紙布の素晴らしさを伝えていくことだけです」
時を掛けて織物の技術を高め続け、紙布の価値を表現してきた津島織物。その芸術ともいえる作品を手にしたとき、私はきっと先人たちのひたすらな情熱と、伝統を受け継ぐ者としての誇りを感じるのだと思う。津島さんの話を伺い、そう確信した。続けることは簡単なことではない。しかも、想いも受け止め続けていくことはさらに難しい。だが、津島さんからは絶対的な自信も感じる。それは津島織物が繋いできた確固たる伝統の技が「証」としてあるからだろう。