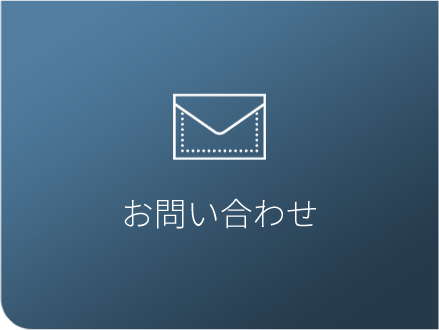宮島最古のお寺が種をまく意味とは。手を合わせ祈ることは世界平和に繋がる。

吉田大裕
Daiyu Yoshida
宮島 [広島県]
吉田大裕(よしだ・だいゆう)
広島県廿日市市出身。宮島で最古の寺院である真言宗御室派の大本山大聖院に生まれ、2016年より、第77代住職である父にもと副住職を務める。日々修行を重ねる傍ら、現代アートや音楽などのイベントを開催し、誰もが気軽にお寺の雰囲気に触れられる活動に力を注いでいる。
1200年以上の歴史を持つ真言宗御室派の大本山大聖院の副住職、吉田大裕さんは、幼い頃より両親にお寺を継ぐことを強いられなかったという。だが、世間の想いはそうではなかった。宮島で最古のお寺の後継者という立場に葛藤しながらも、空海の教えに導かれていった吉田さんの心の動きをたどりながら、お寺の役割や手を合わせ祈ることの意味を伺った。
1200年以上の歴史を持つ、弘法大師空海が開基した大本山大聖院
世界文化遺産にも登録されている、日本三景のひとつ「安芸の宮島」。ここは、古くより島そのものが神として祀られてきた歴史を持ち、正式には「厳島」と呼ばれる。
西暦593年に創建された厳島神社は、かつてこの地を納めた平清盛、毛利氏からも厚く信仰され、寝殿造りの社殿や朱色に塗られた大鳥居などが築かれた。海上に建つそれらの荘厳な美しさは、今もなお多くの人を魅了している。

その宮島にそびえる霊山・弥山。真言宗の開祖である弘法大師空海は、唐での学びから帰国した後この山で修行を行い、大同元年、西暦806年に真言宗御室派の大本山大聖院を開基したと言われている。神仏習合の時代から歴史を重ねてきた大聖院には、空海を祀る「大師堂」、嚴島神社の本地仏、十一面観世音菩薩を祀る「観音堂」、豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に祈願した本尊波切不動明王を安置する「勅願堂」、そして福徳、智恵、降伏の徳を備えた弥山の守護神、三鬼大権現を祈祷する「摩尼殿」などが点在している。さらに、「霊火堂」には、空海が弥山で護摩行を行った際の火が「消えずの火」として1200年の時を経た今でも灯り続け、広島平和記念公園の「ともしびの火」にも受け継がれている。
「当院は檀家を持たない信者寺として、参拝に来られる信者さんと一緒に祈りを捧げることを日々大切にしています。観光客が立ち寄ってくださることもあり、日頃、みなさんにとってなかなか接する機会が少ないお寺を、身近に感じていただく場にもなっています」
そう語るのは、大聖院の副住職を務める吉田大裕さんだ。第77代住職である父のもと修行を積みながら、同時に現代アートや音楽などのイベントを開催し、誰もが気軽にお寺の雰囲気に触れられる活動にも力を入れている。
歴史ある大聖院の継承。その意味を考え続けた日々
宮島で最古の歴史を持つ大聖院の長男として生を受けた吉田さんだが、その印象から気負いを感じることはなく、実に柔軟だ。

「幼い頃から、両親にお寺を継ぐように言われたことは一度もなかったんです。自由に自分の人生を歩めば良いと。ですから、私自身も『継ぐ』ということはあまり意識していませんでした。たまたまお寺の中に家がある、という感覚でしたね」
とはいえ、法要の際には一休さんのような装束を纏うこともあり、周囲からは当然、大聖院の後継者として捉えられていたという。小学校では、同級生から坊主頭ではないことをからかわれたこともあった。「なぜ、みんなと同じような家庭に生まれなかったのか」。幼心にそう感じる吉田さんに「信仰」を意識する出来事が訪れたのは、小学2年生のときだ。
当時、父親から告げられたのは、祖父の弟子になるため髪を剃り仏道への修行に入ることを意味する「得度式」を行うことだった。深い理解もないままに、大好きな祖父のたっての願いを受け入れた吉田さんは、それ以後毎朝、本堂の仏様と数ヶ月後に亡くなった祖父にお茶を供えるのが日課となった。寒い朝でも、風邪で体調が悪い朝でも、欠かさず続けることが役目だった。
「寝坊して学校に遅れそうでも、休む理由にはなりませんでしたから大変でしたよ。ですが、毎朝仏様に手を合わせると、祖父が常に私のそばにいるように感じていました。お天道様が見ているとよく言いますが、それと同じような感覚で、手を合わせる度に悪いことはできないと思っていたものです。仏教には、人は良い行いをすれば良い報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるという『因果応報』の教えがありますが、そのときに学んだような気がします」
だが、その後もお寺を継ぐことを素直に受け入れられないまま中学校入学と同時に島を離れ、サッカーに没頭した。同級生たちには、自らが大聖院の長男であることはあえて告げなかった。
その後も島外に暮らしながら高校生活を送っていたある日、初めてお寺である実家に親しい友人を招いたという。
「『すごい!』と、驚いていました。しかも、お寺を継ぐことに悩んでいた私に向かって、友達自身が継いでもいいと。その言葉が素直に嬉しかったですし、自分の自信にも繋がりました」

何のためにお寺があるのか?何のためにお坊さんになるのか?大聖院を継ぐということは?
少しずつその意味に近づき始めた吉田さんだったが、それでもなお、10代後半は答えを見つけ出せずにいたという。
そして、より広い世界を見るために東京へ移り大学生活をスタート。経営学を学びながら、同時に力を注いだのが「認定NPO法人 鎌倉てらこや」の活動だった。
精神科医である森下一氏の呼びかけで始まった、お寺を拠点としたこの活動は、親だけではなく地域に暮らす様々な立場の大人との関わりの中で子どもたちを見守り、生きる力と心を育んでいく「複眼の教育」を掲げている。現代版の寺子屋で同世代の若者がイキイキと活動する姿を見て、自らもその一員になった。在学中に起きた東日本大震災では、被災地でもてらこや活動を行い、体を動かし人と関わりながら活動することの喜びを感じたという。
「一度は社会人として働きたいという希望もありましたので、大学卒業後もてらこやの活動を継続していました。そんなとき、数年後に父親が修行で大聖院を離れるという話が挙がり、私もついに継ぐかどうかの決断を迫られたんです。そして、お寺に戻ることを決意しました」
自らの生まれや生い立ち故に葛藤を重ねながらも、次第に大聖院を継承することへ導かれていった吉田さんは、東京を離れ、真言宗御室派総本山である京都の仁和寺での厳しい修行へ。そこでの日々は、お寺を継承することへの想いを強くするものだったそうだ。

「なにより、人のために祈る僧侶の姿に胸を打たれました。同時に、自分自身を整えることも大切だと学んだんです。というのも、例えば約100日間に及ぶ修行は、一日三度同じことを繰り返すのですが、病気になろうが、家族に不幸が起ころうが、一度でも休むと最初からやり直しとなります。決して休むことが許されない修行に向かうには、まずは自分の体調管理を行い、その上で家族の健康や安全も祈り続けること、信じ続けることが必要なんです。
修行を積み重ねるうちに、空海さんと真言宗の教えの奥深さを感じ、仏教への情熱に火がつきました。今だに学びの毎日ですが、これが天職だと感じています」
お寺は社会の公器。誰にとっても身近な存在になるために。
仁和寺での修行を終え、生まれ故郷である宮島に戻った吉田さんがまず感じたことは、大聖院の偉大さと、静かに佇む弥山の美しさだった。かつては反抗心すら抱いていた環境が素晴らしいものだと気付かされたという。
そしてそこから、副住職としての歩みが始まる。

「大聖院は宮島の中でも一番奥に位置するお寺です。しかも、最初の仁王門からは100段の石段が続きます。それでもわざわざ足を運んでくださった方に、『お参りして良かった』『また訪れたい』と感じていただくために、お寺として何ができるのかということを常に考えています。幸い、住職である父も理解してくれますので、私が思いついたことを自由に挑戦させてもらっています」
僧侶に境内を案内してもらいながらその長い歴史をたどる体験や、弥山の頂上での護摩祈祷など、空海の教えに触れる取り組みはもちろん、気軽にお寺の雰囲気を感じられるイベントも数多く開催している。そこに関わるのは一見、仏教とはかけ離れているかのような人々も含まれる。ミュージシャン、コラージュアーティスト、映像クリエイター、サウンドデザイナー、DJなどが大聖院と弥山を舞台に最新のアートを生み出すこともあるのだ。さらに地域の方が自らの活動を語り、披露する場として使われることもある。「歴史あるお寺でそんなことまで」という声も聞かれるが、吉田さんの思いは一貫している。

「昔のようにお寺にお参りすることが日常だった頃とは違います。今は、まず足を運んでいただくきっかけづくりからだと思っているんです。そのためには、お寺と縁がない方にも興味を持っていただけるような種まきが必要。宮島は遠くからも観光客が訪れますので、その方々が大聖院での体験を地元に持ち帰れば、そこでお寺にお参りするきっかけになるかもしれませんし、もしかすると、お寺で新たな取り組みが始まるかもしれません。大聖院でのイベントは、決してここだけのことを考えて企画しているわけではないんです」
SNSの発信など、良いと思うことを形にしている吉田さんだが、日本で最も格式が高いといわれる仁和寺はもちろん、そもそもお寺は「社会の公器」としての役割を担っていたという。寺子屋が開かれ、祭りや行事も行われる地域の拠点として、人々が集い、語り、学び、発信する場であったお寺は、今もなお地域のものであり地域の人々のものなのだ。逆をいえば、100年後、1000年後に、地域の人が必要ないと思えばお寺は消滅してしまう。そこで問われるのは、お寺がいかに地域に根付いた活動をしているかということ、そして、地域の人々に必要とされているかということだ。
公器として求められれば、決して「ノー」とは言わないのが「吉田家」のモットー。あくまでも実現できる方法を探し続ける。それが大聖院の、吉田家の種まきなのだ。
「高校生のとき、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世が大聖院でお過ごしになったんです。そのときにいただいた、『結果はどうであれ、良いと思うことは続けなさい』という言葉も、私の想いの礎になっています」

古代の人々は、朝日が昇ると、太陽や山に手を合わせ一日の無事を祈り、日暮にはその一日を生きながらえたことに感謝するため、再び手を合わせたという。科学や文明が進歩した今の時代でも、大自然の力には敵わないと感じることが度々起こり、人間の無力さを痛感することもある。
「ですが、その中で自分の命をどう全うするのか、ということが大切だと感じています。無事でいられること、健康であること、おいしい食事をいただけることの全ては、当たり前ではなく感謝すべきことなんです。それを、ありがたいこと、幸せなことだと気付ける人が増えればと願っています。手を合わせ祈ることが、自分を振り返り、また周囲の人に想いを馳せるきっかけになればいい。それがお寺の役割かもしれません。
私は思うんです。手を合わせ祈ることは世界平和に繋がると」
未来へ繋いでいきたいものは何か?
最後に、吉田さんが未来に繋ぎたいものを聞いてみた。
“空海さんの教えですかね。1200年以上前の方なのに、その教えは現代こそ皆さまに知ってもらいたい”
「空海さんの教えこそ、人類の本質や、私たちが生きていく上で大切にすべきことを説いてくださっている。
空海さんの瞑想の一つに、自らの心を満月に例えるものがあります。その月の輪を大きく広げていき自分を包み込むイメージができたら、さらに月を大きくして、家族や知人、同じ地域に暮らす人をその輪に加えていく。そして最後には地球上のすべての人も加えられる程にその輪を広げていくんです。そうすることで、私たちがみな、同じ地球で暮らしを共にする存在、愛を持って接するべき存在だということに気付かされます。その想いが共有できれば、一瞬かもしれませんが戦争も止まるかもしれない。自分一人のためではなく、みんなのために祈り、行動ができる人が増えるかもしれない。
私がやるべきことは、まだまだたくさんあります。どんな種まきをしようかと、いつも想いを巡らせています」
社会の公器として求められるものを形にしていく吉田さんの姿に、お寺の無限の可能性を感じる。その種まきこそが、祈りに繋がり、世界平和に繋がると信じたい。武器を持つのではなく、手を合わせるというシンプルな行為こそが、なにが大切かを見極める最良の手段なのかもしれない。