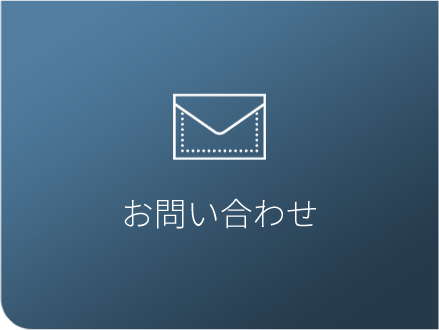祖父から孫へ受け継がれた故郷の酒。人の絆を育む「泡盛」を未来へ繋ぐ

池原 文子
Ayako Ikehara
国頭郡大宜味村 [沖縄県]
池原 文子(いけはら・あやこ)
沖縄県大宜味村出身。「やんばる酒造」5代目、代表取締役社長。大学で醸造学を学び、海外留学を経験したのち2013年に家業へ。祖父や地域の人々に支えられて育ち、泡盛で結ぶ人の絆を未来に残そうと力を注ぐ。泡盛に加え、地元食材を使ったリキュールやシロップ開発にも取り組み、地域と酒造所、そしてここを訪れる人々とを繋ぐ活動を続ける。
沖縄本島北部、世界自然遺産「やんばる」に位置する大宜味村田嘉里。ここに根を下ろす「やんばる酒造」は、地域の人々の出資により誕生し、70年以上にわたり「泡盛」の製造を続けてきた。5代目を務めるのは、「まるた娘」と呼ばれ親しまれる池原文子さん。祖父の背中を追い、酒造りに携わるようになった池原さんは、泡盛を単なる酒ではなく、人と人を繋ぎ、地域を支える大切な文化と捉える。泡盛の魅力を未来へと紡ぐその活動と思いに迫った。
泡盛なくして語れない、田嘉里の暮らし
「高校生の頃からずっと、『まるた娘』と呼ばれています。というのも、うちの酒造所で造るお酒の銘柄が『まるた』。トレードマークも丸い円の中に『田』の文字なんです。ただ私も4人の子どもの母親なので、そろそろ娘に『まるた娘』の名を譲らないといけないかな、と思っています」
そう、朗らかに話すのは、「やんばる酒造」5代目の池原文子さん。人懐っこい笑顔が、交わる人全員を虜にしてしまう、そんな女性だ。
酒造所があるのは、沖縄県北部に位置する世界自然遺産「やんばる」地方。所在は大宜味村だが、この地方を形成する国頭村、東村の境目に位置し、山々に囲まれた田嘉里地区の中心に建つ。造っているのは沖縄の伝統的な蒸留酒、「泡盛」。亜熱帯の気候で腐敗しないよう、そのアルコール度数は一般的なものでも25〜30度。なかには50度を超えるものもあるという。
「この集落の人たちが集まる場には、昔からいつも『泡盛』がありました。泡盛は、私たちにとって島酒。絆を深めるために、なくてはならない存在なんです」

その言葉通り、盆正月や祭りのとき、また、集落全体で行われる何かしらの作業の後には、必ず人々の輪の中心に泡盛が置かれる。酒を酌み交わし、わいわいと楽しく語らい合うなかで、お互いの結びつきを強めていくのだ。
「ここで生まれ育った私にとって、子どもの頃から当たり前にある光景です。人と人との距離も近いので、顔を見るだけで『あんたは、池原の孫だね』と、おじいやおばあが声を掛けてくれていました。その近しさがとても温かくて心地良かったですね」
祖父の温かさ、酒造所の居心地の良さが支えた未来への決意
やんばる酒造の成り立ちは、この集落の人たちがお金を出し合い、1950年に「田嘉里酒造所」を創業したことにある。そこで中心的存在となったのが大嶺深水氏。池原さんの祖母の叔父に当たる人で、住人たちから厚い信頼を寄せられていたという。そこからしばらくして、管理運営を任されたのが、池原さんの祖父、池原三郎氏である。杜氏を務めながら、配当という形で泡盛を集落の人に配るだけではなく、酒造所を後世に繋いでいくために利益を生み出していこうと尽力した人だ。
その祖父から深い愛情を受けたという池原さんは、幼い頃から毎日のように酒造所に足を運んだという。祖父だけではなく、酒造所で働く人たち皆んなに孫のようにかわいがられた池原さんだが、まさか自分がそこで働くことになるとは思ってもみなかったようだ。
「私は一度、高校を辞めているんです。思い返せば、思春期特有の迷いのようなものがあったんでしょうね。そのときに、やさしく接してくれたのが祖父だったんです。時間を持て余している私に、『何もやることがないなら、おじいと一緒に働くか?』と言ってくれて。しかも、手伝うようになった私の様子を見て、酒造所の皆さんもやさしく見守ってくれたんです。『あんたは、まだまだ頑張れる子だよ。やればできる子だよ』と、誰一人として私を否定しなかった。
そんな状況で過ごすうちに、自然と祖父たちのために役に立ちたいと思うようになったんです。私を温かく見守ってくれた人たちのためにできることは何だろうと、考えるようになりました」
そして、池原さんは再び高校に。その後、大学で醸造学を習得し海外留学を経て、「跡継ぎ」になると心を決め、2013年に酒造所に戻った。
アイデンティティの一部である故郷の酒
現在、沖縄には47の酒造所がある。県内の市町村数が41であることを考えれば、各集落や地域に一つは酒造所があると言ってもおかしくはない。つまり、沖縄に暮らす人にとって、泡盛は日常とともにある酒なのだ。酒造所の規模は、どこもそれほど大きくないものの、地域に根差した特徴豊かな酒が造られている。
「田嘉里も同じです。酒造所に触れずに集落の歴史を語ることはできない、と言われるほど、私たちの暮らしと泡盛の繋がりは切っても切れません。故郷の泡盛を、誰もが『自分たちのお酒』と認識しているんです。だから、仮に遠方に出掛けたとしても、故郷のお酒か、あるいは故郷に近い場所のお酒をいただきます。もはや、泡盛は私たちのアイデンティティの一部なんです」
やんばる酒造の酒の7割が、地域で消費されているのもその証だろう。田嘉里集落の人々の歴史は、間違いなく泡盛とともに紡がれたのだ。
「たとえ沖縄を遠く離れたとしても、味わうことで故郷を思い出し、自分の存在やルーツを改めて意識できる。それが泡盛の力ですね。このすばらしい価値を次の世代にどう繋いでいくのかが、これからの私の課題。そのためにはまず、やんばる酒造のこと、私たちの製品のことを知ってもらうことが大切だと思っています」


沖縄の方言では、妻のことを「トゥジ」という。かつての日本では、女性が酒造りを担っており、その名残なのだそうだ。沖縄に女性杜氏が多かったかどうかは定かでないが、池原さんも、やんばる酒造に戻った頃には、大学で学んだことを活かし杜氏を志していた。
だが、いざ現場に立ってみると、造った製品をお客様に届ける作業も重要だと気付く。もちろん、製品を知ってもらえないことには、酒造りも安心して行えない。
「今は、杜氏が自らの色を酒造りに存分に活かせるよう、その土台作りに専念しています。ここで働く皆んなが、自分たちが手掛けたお酒に誇りを持てる、そんな環境を整えるが私の役割です」
やんばるの泡盛から広がる、人を繋ぐコミュニティ
やんばる酒造の看板商品は、言うまでもなく泡盛である。その源となっているのが、世界自然遺産であるやんばるの森から湧き出す清らかな水だ。ミネラルをほどよく含んだその水は、酒を醸す際に重要な黒麹菌の力を引き出し、深く豊かな風味をもたらしてくれる。
「水がおいしいと良いお酒が仕込めるといいますが、これも大自然やんばるの恩恵です。ここで造るお酒の特徴は、原料であるお米の香ばしさが感じられることと、口当たりがとてもまろやかなこと。水の良さがあるからこその味わいです」
ただ、池原さんがやんばる酒造に戻って以降、それまでの「泡盛」中心の製造にとどまらず、ラインナップの拡充にも力を注いでいる。
例えば、地元で育つバナナや、現地の方言で「カラキ」と呼ばれるシナモンを使ったリキュールを開発し、新たなファンを増やしている。また、池原さん自身が妊娠中にお酒を飲めなかったことをきっかけに、この地域でしか味わえない希少な果物を使ったシロップやジャムなども製造。年齢問わず、またお酒が飲めない人に対しても、間口を広げているのだ。さらに、酒造所の一角に構えたショップでは試飲もでき、ここを訪れる観光客との交流の場にもなっている。


「泡盛は、造られている場所で飲むのが一番だと思っているんです。緑豊かな山々をはじめ、やんばるの大自然を見て、空気に触れて、この酒造所で誰がどんな思いで酒造りに向き合っているかを知っていただきたいんです」
そう話す池原さんは、観光客に工場を案内する際、他の酒造所やそこで造る泡盛を紹介することもあるという。また、やんばる各地の観光スポットも積極的に勧める。なぜなら、「沖縄を、やんばるを好きになってほしい」から。
その思いは、数年前からスタートさせた「やんばるもあい」にも繋がっている。
そもそも、もあい(模合)とは、複数人がグループを作って毎月一定金額を積み立て、何かしらの問題が起こったときに、それを元手にサポートするという相互扶助の仕組みのこと。現在は、メンバーの食事会や旅行に当てられることが多いという。
そのシステムをアレンジしたのが「やんばるもあい」だ。もあい仲間となったお客様が酒造所に会費を納めることで、定期的に泡盛や地域で育ったマンゴー、島らっきょうなどが届き、酒造所で年に1度開かれる「本場のやんばるもあい」にも参加できる。
「コンセプトは、遠い親戚のようなお付き合い。田舎でできたものを送り、また、田舎に帰るような感覚でやんばるに来ていただきたいと思っています。実際に、全国各地に広がる『もあい仲間』からは、『こんなに沖縄を楽しめたのは初めて』『家族のように無条件に受け入れてくれる場所は他にない』と、感想をいただいています。
酒造所が中心となって、やんばるの人と、この地を訪れる人たちを繋げるコミュニティを作ること。それが私たちのお酒が存在する意味です。やはり、お酒は人を繋ぐ最高のツールですね」
来へ繋いでいきたいものは何か?
最後に、池原さんに未来へ繋いでいきたいものは何か、と尋ねた。
「近頃は、各集落のセンターや共同売店などが過疎高齢化の波で、続々と姿を消しています。それまで、地域の拠点だったところに人の姿がないんです。だからこそ、やんばる酒造はいつでも扉を開け放って、訪れる人たちを温かく迎え入れる場所であり続けたい。次の世代も、さらにその次の世代もずっと。そのためには、人の絆を結ぶ泡盛の力を、きちんと言葉にして伝えていくことも大切だと思っています」
やんばるは、長寿の里でもある。自らの畑で農作物を育て、それらをよく食べよく眠る。そして翌日には再び畑に向かう。この地に暮らすおじいやおばあの日常であり、長生きの秘訣だ。だが、なにより大事なのは、集落内でのコミュニケーション、と池原さんは話す。そのときに、「泡盛」が重要な役割を担うのだ。
やんばるの大自然に抱かれ、その恩恵とともにある人々の暮らしには、いつも穏やかな笑顔が広がる。なにより感銘を受けるのは、やんばるの日常のすべてが池原さんの原風景であり、さらに、子どもたちにも受け継がれようとしていることだ。その中心にある泡盛というお酒は、人を繋ぎ、人を育む力を持っている。