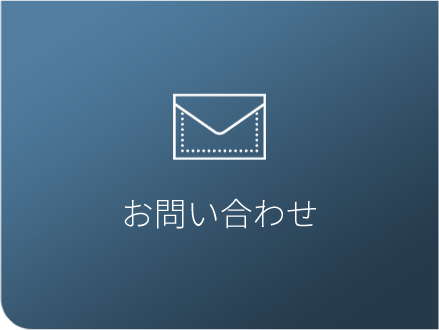熊本から世界へ。「武士の芸術」で伝える生き方の哲学

太田 光柾
Mitsumasa Ota
熊本市 [熊本県]
太田 光柾(おおた・みつまさ)
1973年熊本市出身。全日本居合道連盟無双直伝英信流八段、グラフィックデザイナー、画家。父の影響で幼いころより、居合道と熊本の文化に触れる。海外での経験を機に、武士の芸術への理解を深め、居合道やアートを通してその意味するものを国内外で紹介する。現在は伝統技術をもとにした地域振興にも力を注ぐ。
グラフィックデザイナーとしてフランスを訪れた太田光柾さんは、自分が日本人であること、そして幼少期から身近にあった居合道や刀の存在に、改めて向き合うことになる。そこで気付いたのは、武士の精神に宿る、武術を超えた「生き方の哲学」だった。宮本武蔵の思想を受け継ぎ、「武士の芸術」を海外へも広めようと活動する太田さんの歩みが示すものとは。詳しく伺った
海外で意識した、「日本人」としての自分
「幼少期から実家には十数振りの刀があり、父が手入れする姿を見て育ちました。当時は、よその家もそうなのだろうと思っていましたね」
太田さんの父は、宮本武蔵・二天一流十五代宗家(鶴田派)、松永展幸先生に弟子入りした太田誠二氏である。自宅には、居合道の道場もあったため、松永展幸先生をはじめ高名な先生方、刀鍛冶に鞘師、研ぎ師といった職人たちにもかわいがってもらった記憶があるそうだ。ただ、太田さんの若い頃の関心は、もっぱら欧米の音楽やアートに向けられていたという。
20代後半を迎えた太田さんは、化粧品会社のグラフィックデザイナーとしてフランスを訪れる。10代の頃からインスパイアされた欧米のデザインをもとに描いた作品が、現地のクリエイターたちに受け入れられると信じて。だが、評価されたのはそれではなく、意外にも日本の家紋をデザインした自作のTシャツだった。

「そのとき初めて、自分が日本人であることを意識したんです。育ってきた環境を振り返るきっかけとなった出来事でした」
日本の伝統文化が、海外の人々には新鮮に映る。そのとき、これまで意識していなかった「和」のデザインに世界へ通じる価値があることを、太田さんは確信する。
実家に保管されている肥後鐔(※1)や日本刀の装飾は、故郷・熊本を治めた細川家が育んだ芸術品であり、そこには茶道の大家・千利休の「侘び寂び」(※2)が色濃く影響している。さらに、禅寺の庭園に見られる枯山水(※3)には、自然の姿そのものを映し出す日本独自の美意識がある。それらのことを、改めて意識したのだ。
(※1)肥後鐔(ひごつば):鐔(つば)とは、日本刀における柄(つか)と刃(は)との間に取り付けられる金具。肥後鐔は江戸時代に肥後国(現在の熊本県)で作られ、過度な装飾を避け、控えめで洗練されたデザインが特徴。
(※2)侘び寂び(わびさび):不完全さやはかなさ、静けさの中にある美しさを感じ取る日本独自の美意識。簡素で古びたもの、余白や沈黙の中にある美を重んじるのが特徴。
(※3)枯山水(かれさんすい):石や砂で自然風景を表す日本庭園の様式。禅の精神と深く結びつき、静寂と抽象の美を体現する。
「斬る技術」ではなく「己と向き合う道」。武士の芸術に宿る精神性とは
フランスで、自分が日本人であることを強く意識した太田さんは、居合道や日本刀が身近にある環境が「特別」だったことに気付く。そして、次第に「武士の芸術」に関心を抱くようになり、再び居合道にも打ち込みはじめる。そこで改めて感じた「礼」の多さ。居合道は、神に、刀に、師範に、共に稽古する仲間にも礼をする。「単に人を斬る行為であれば、礼は必要ないはず。なぜそこまで礼を尽くすのか」。疑問に感じた太田さんは、その歴史や意味を掘り下げていく。
「『太刀』という言葉の語源が『断つ』だと、そのとき知りました。つまり居合道は、敵に勝つことよりも、自分の弱さを断つことが重んじらているのです」
日本における「刀」は、諸外国の武器とは異なり、あくまでも自分自身と向き合う術であることを理解した太田さん。加えて、居合道の根幹には、日本人の精神文化の礎である「神道」(※4)の存在があることも知る。
「居合道は、人を斬る技術を伝えるものではなく、その『道』には、一生をかけて己の生き方を問い続ける、という意味が込められているんです。
書道や華道、茶道にも共通する概念であり、すべて芸術の域まで高められています。それに気付いたとき、大きな衝撃を受けました」


さらに、日本の国宝のうち約半数が「刀」であるという事実は、この国が歴史上、刀をいかに重んじてきたかを物語っている、と太田さんは説明する。歴代天皇が継承してきた宝物「三種の神器」の一つである「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」が、人を殺めるためではなく「草を薙ぐ」ためのものであった、という事実も忘れてはならない。
「刀は、神に供える神聖なもの。そうした文化を、日本人の多くは知らずに過ごしています。私の役目は、その意味を日本人はもちろん、海外の方にも伝えることだと感じたんです」
そして2010年、太田さんは武士の芸術をアートで表現すべく、熊本市の島田美術館で「肥後鐔の世界と武士道美術展」を開催する。展示したのは、フランスでの経験を機に描き始めた肥後鐔をテーマにした絵画の数々。結果は、予想を遥かに超える大反響だった。
またこの年、太田さんは全日本居合道連盟全国大会六段で優勝。「武士の芸術」の伝承者として、大きな一歩を踏み出した。
(※4)神道(しんとう):日本固有の宗教であり、八百万(やおよろず)の神々を信仰する自然崇拝を基盤とした信仰体系で、特定の開祖や経典はない。清らかな心、感謝の心を持って、神々や自然、祖先との調和を重んじる日本人の精神文化の根源。
剣豪であり、芸術家であった宮本武蔵から学ぶこと
太田さんが活動の核とするもう一つの存在がある。それは、熊本で晩年を過ごした宮本武蔵だ。武蔵は、60戦無敗の剣豪として広く知られているが、同時に、絵画や彫刻、書などに秀でた芸術家でもあった。その生涯の哲学をまとめた兵法書『五輪書』は、「地・水・火・風・空」の五巻で構成され、戦い方のみならず、生き方そのものに通じる教えが込められている。
武蔵は、「五輪書」の最終「空の巻」でこう説いている。「空は善なり、かつ悪なし」。
己の欲やこだわり、勝ち負けといった感情や執着から解き放たれた「無心の境地」こそが最も優れている、という教えである。勝つことの先にある心の平穏、そして、武蔵が生涯をかけて向き合った『どう生きるのか』という問い。太田さんは、その精神性を、居合道や絵画を通じて多くの人に伝えようとしているのだ。
「さらに、武蔵の生き方は現代のビジネスにも通じます」と、太田さんは続ける。
「武蔵は、三つの方法で自らをブランディングしていたんです。
一つ目は、一刀流が主流だった時代に二刀流を編み出し、あえて異なる視点から道を切り拓いたこと。二つ目は、文化芸術を重んじた細川家に自らを剣豪としてだけでなく芸術家としても認めさせたこと。そして三つ目が、自らの歩みと思想を『五輪書』にまとめ、世に遺したこと。
私たちは時代を超え、あらゆる場面で武蔵から学ぶことができるんです」
居合道の体験を通して伝える、心の平穏に通じる「美」

2019年より、太田さんは海外からの来日者を対象に「武士の芸術」を伝えようと、居合道の体験コンテンツを提供している。その際に軸となっているのは「美しさ」だという。
「おそらく参加者は、刀で何かを斬るショーのようなものを期待されると思うのですが、私達の流派ではそのような行為を行いません。
武士の芸術性や精神性など、それらの根底には心の平穏に通じる『美』があります。それを居合道の体験で感じていただきたいんです」
実際に参加者からは、「心の安らぎ、マインドフルネスを得ることができた」「『動』ではなく、心の中に『静』を感じることができた」という感想も聞かれるそうだ。
「先日、ニューヨークで行った居合道の体験会でもこんなことがありました。参加した20代前半くらいの女性が、『私が求めているものは、このまちではなく日本にある』とおっしゃったんです。ニューヨークは資本主義の象徴ともいえる、物や情報が溢れる都市。それだけに、競争から逃れられず、安らぎのない場所だと彼女は感じているようでした。
『日本に根付く精神性の美しさに憧れている』という彼女は、近々日本に訪れたいと話してくれました」
さらに太田さんは、体験の際に、参加者に必ず伝える「史実」があるともいう。
「1600年の関ヶ原の戦いの際、わずか500の兵力とともに籠城する細川幽斎が、敵である石田三成の兵15,000に包囲されるという局面がありました。このときに動いたのが、後陽成天皇です。実は当時、細川幽斎は『古今和歌集』の秘儀である『古今伝授』唯一の継承者であり、もし幽斎が命を落とすようなことがあれば、歌道の正統が絶えると考えられたんです。結果的に、戦いは避けられ、細川幽斎の命は守られました。
天下を分けるほどの大合戦で起きた奇跡は、伝統や文化を重んじる日本人の象徴ともいえる出来事。承継への確固たる意思は争いを止める力を持つ、と私たちに教えてくれます。
この史実は熊本の宝であると同時に、日本の宝です。世界各地で紛争が起きている今、400年以上前のこの奇跡の意味を、改めて伝えるべきだと思っています」
現在、熊本の地で、伝統技術の継承やそれをきっかけとした地域振興にも力を注いでいる太田さん。2017年に菊池市で開催した、「菊池一族と延寿鍛冶展」もその一つだ。同市で700年の歴史を持つ刀鍛冶の文化に光を当てようと企画された展覧会は、国内のアニメやゲームのブームも追い風となり、全国から5000人以上の来場者を集めた。若い世代や地元住民の間にも地域文化の再発見を促したこの取り組みは、今や菊池市を代表する観光資源になっている。
また太田さんは、熊本県をはじめ九州各県の侍文化をつなぐ観光ルート構想も描いている。各地に残る伝統や文化を線で結び、日本人や外国人観光客に触れてもらうことで、後継者不足や経済的課題にも貢献したいと熱く語る。

未来へ繋いでいきたいものは何か?
最後に、太田さんに未来へ繋いでいきたいものは何か、と尋ねた。すると、次のようなエピソードを語ってくれた。
「2016年に起きた熊本地震のとき、水や食料を買おうと、父と一緒にコンビニに寄ったんです。このタイミングで買っておかなければ、明日には手に入れることができなくなるかもしれない。そう思った私は、つい買い占めようとしました。
その姿を見て父がこう言ったんです。『他の人の分も残しておきなさい』。
ふと我に帰った私は、父の一言こそがまさに居合道の精神なのだと感じ、恥ずかしくなりました。
東日本大震災のときも、日本人は略奪や暴に走らず、規律を乱すことはありませんでした。その姿にこそ居合道の精神があると気付き、自分の未熟さを痛感したんです。
父の言葉は、私にとって生きていく上での指針であり目標です。そして、その精神は世界中の人たちにも通じると信じています」
居合道や武士の芸術の根幹を成す、自らの生き方を見つめ、いかに歩むのかを問い続ける姿勢。生涯をかけても、答えを見出すことは難しいかもしれない。だが、その行いこそが人の心に平穏をもたらし、社会を平和へと導く鍵になる。
太田さんは、今を生きる私たちへ、そして未来を生きる人たちへ、己の「道」に思いを馳せるきっかけを与えてくれているのだろう。